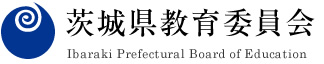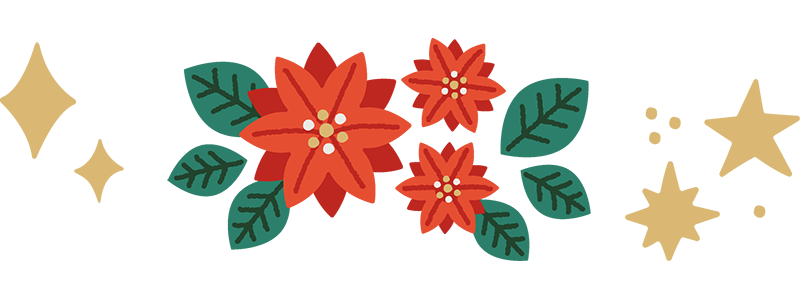令和7年6月 教育長定例記者会見
教育委員会では、令和7年6月27日(金)、教育長定例記者会見を実施しました。内容は下記のとおりです。
会見要旨
6月の定例記者会見の発表項目は3点です。
次世代グローバルリーダー育成事業における取組について「NGGL修了生が世界トップクラスの学びを語る!」
(資料「次世代グローバルリーダー育成事業における取組について「NGGL修了生が世界トップクラスの学びを語る!」」に基づき説明)
茨城県では、学習意欲の高い中高生を対象に、平成30年度から次世代グローバルリーダー育成プログラム、通称NGGLとして、本事業を実施しています。受講生は週に1回、オンライン形式での英語講座に取り組んでいるほかに、年間5回、県庁をはじめとする会場に集まり、グローバル人財に必要な思考力、探究力、リーダーシップ等を学んでおります。
その一環として、本プログラムを修了した方で、「QS世界大学ランキング」第2位のインペリアル・カレッジ・ロンドンへ進学した川田さんと受講生82名が交流を図る取組についてご紹介をいたします。世界トップレベルの大学での刺激的な学び、大学院コースへの進学、そしてNGGLでの経験がどのように現在の学びや将来の展望に繋がっているのか、具体的なエピソードをご本人からお話をいただく予定でございます。川田さんの活躍は、NGGLのテーマ、「茨城発・世界トップレベルへの挑戦、そして更なる飛躍」を具現化したものでございまして、多くの読者や視聴者の皆様に興味を持っていただけると確信しております。当日は、7月下旬に韓国・ソウルで行われるワールド・スカラーズ・カップ世界大会に向けての研修も予定しているほか、国際社会で活躍するために重要な国際問題解決力、交渉力、論理的思考力を高める模擬国連演習に向けた事前研修を予定しております。日時及び場所は、資料に記載のとおりでございますので、ぜひ、取材などをしていただければ幸いでございます。
令和7年度教員再チャレンジ研修会の開催について
(資料「令和7年度教員再チャレンジ研修会の開催について」に基づき説明)
この研修会は令和4年度から継続して開催しているもので、「教員免許状を所有していますが教職経験がない方」、「過去に教職経験がありますが教職から離れている方」等に、現在の学校教育や講師登録に関する研修を行うことで、常勤講師や非常勤講師として働くことへの不安の解消を図ることを目的としているものです。
第1回から第5回の日時及び会場につきましては、資料に記載のとおりでございますが、今年度は受講者の増加を図るため、開始時期を2ヶ月前倒ししまして、県内5地域で開催することにいたしました。研修会は、各回2時間の予定で、会場参加が難しい方向けには、第1回の録画のオンデマンド配信を行うこととしております。研修内容については、資料記載の4項目になり、研修会終了後に、講師登録会及び個別相談会を実施してまいります。受講対象者については、茨城県内の学校に勤務を希望する方で、教員免許状を所有しているが、教職経験がない方など先ほど説明した方が対象でございます。申込み方法は、茨城電子申請・届出サービスで受け付けをしてまいります。この研修会についても、教員の確保という点で非常に重要な位置付けと考えております。
令和9年度以降の次期県立高等学校改革プラン策定に係る県高等学校審議会の開催等について
(資料「令和9年度以降の次期県立高等学校改革プラン策定に係る県高等学校審議会の開催等について」に基づき説明)
まず、1ページ目の高等学校審議会についてです。高等学校審議会は、茨城県行政組織条例に定められております教育委員会の付属機関として、高等学校の編成や産業教育の振興に関する重要事項等についての調査審議が担任事項でございます。前回の審議会は、平成29年度から平成30年度にかけて開催され、その審議会の答申に基づきまして、県立高校改革プランを策定し、中高一貫教育校の設置、学科の改編など、県立高校教育の改善・充実に現在努めているところでございます。現行の改革プランの計画期間は令和8年度まででございまして、今後の高校教育改革の方向性についてご審議いただくため、今回約8年ぶりの審議会を開催するものでございます。
次に、2ページ目の現状についてです。高校教育を取り巻く環境の変化と新たなニーズということで、昨年、「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会(論点整理)」が出されるなど、次の学習指導要領の策定に向けて、国の動きが大変活発化することが当然想定されてまいります。これまでも、少子化、グローバル化、生徒の多様化といった高校教育を取り巻く環境は変化しており、今後は、学級規模の縮小化や外国人生徒の増など、それぞれの変化が更に加速していくことも想定していく必要がございます。これらのことを踏まえ、外部有識者の意見を聴取する審議会を開催し、今後の県立高校の在り方について答申をいただくこととしたところでございます。
続いて3ページ目になりますが、次期改革プランの計画期間等について、基本的な方向性は現行の県立高校改革プランの踏襲と考えております。計画期間は7年間とし、今回の高等学校審議会の答申を踏まえまして、基本的な方向性を示す「基本プラン」を策定する予定でございます。その上で、産業界や地域の新たなニーズ、少子化の加速、生徒の多様化、外国人生徒増などの社会の変化などを適時に反映させるため、具体的な実施内容を示す「実施プラン」は、Ⅰ期4年とⅡ期3年に分けて策定をする予定でございます。
最後になりますが、開催期間、委員構成、諮問事項についてです。開催期間は令和7年7月から11月を予定しております。2回の総会と3回の専門部会での審議を想定しております。ただし、現段階の期間、回数の想定でありまして、第1回の総会において、審議会委員による協議で開催日程が確定する運びでございますので、開催期間が、その審議の進捗によっては延びることもありうるということをお含みおきください。委員構成は、県高等学校審議会規則に従い、産業経済関係団体、教育関係団体、行政機関、学識経験者の区分から、18名に教育委員会が委嘱することとなります。なお、本県では、男女共同参画社会の実現に向け、県の政策方針決定過程の女性の参画促進に努めているところでございまして、本審議会でもその趣旨を踏まえまして、女性委員の割合は50%としております。諮問事項は、「人口減少をはじめとする様々な社会の変化に対応した活力と魅力ある学校・学科の在り方について」とし、現行の改革プランを踏襲しつつも、前回審議会以降の、社会の新たな変化などに対応するため、「学校の適正規模・適正配置」「魅力ある学校・学科」「選ばれる県立高校であるための魅力訴求」の3つの視点でご審議いただく予定でございます。第1回総会は公開での実施を予定しております。日程等を、改めて皆様にもお知らせしてまいりますので、ぜひ取材などをしていただければ幸いでございます。
本日の発表項目に関する説明は以上になります。
茨城県教育庁 総務企画部 総務課 総務担当(広報・広聴)
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5148
FAX番号:029-301-5139
メールアドレス:kyoikusomu8@pref.ibaraki.lg.jp