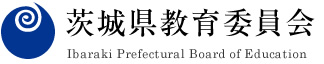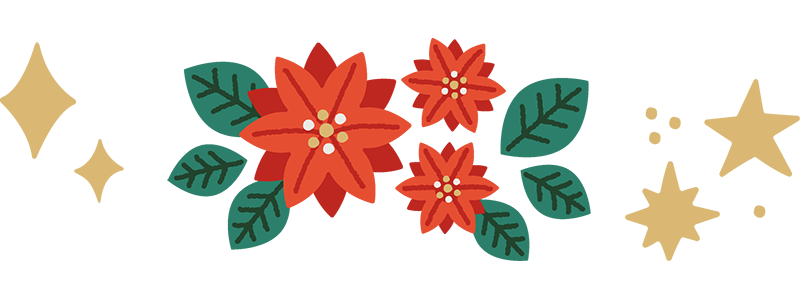令和7年8月 教育長定例記者会見
教育委員会では、令和7年8月26日(火)、教育長定例記者会見を実施しました。内容は下記のとおりです。
会見要旨
8月の定例記者会見の発表項目は2点です。
次年度の教員選考試験について
(資料「次年度の教員選考試験について」に基づき説明)
毎年、教員選考試験の状況を分析し、次年度に向けて制度の見直しを行ってきました。今年度の試験の状況は、昨年度と比べ、全体の志願者数は143名の増加、志願倍率は3.16倍となりましたが、小学校教諭の志願者数は72名減少し、志願倍率は1.75倍でした。また、特別支援学校教諭の志願者数は増加しましたが、志願倍率は2年連続で2倍を下回りました。小学校教諭および特別支援学校教諭の確保について分析を行い、検討を重ねた結果、次年度から試験制度を一部見直すこととしました。
小学校教諭の試験制度の見直しは、小学校の「体育」専科教員の採用(中学校・保健体育との併願の新設)と、受験資格の拡大[中学校または高等学校の教員免許状を持つ者](小学校教諭への転換)を行います。特別支援学校教諭の試験制度の見直しは、受験資格の拡大「教員免許状を持たない社会人経験者」(社会人経験者採用)になります。志願倍率の低い小学校教諭と特別支援学校の試験制度の見直しにより、志願者数の増加を図り、質の高い教員を確保してまいれればと考えているところです。
小学校教諭の現状について、倍率が下がっていることを説明しましたが、定年退職者の増加により、必要な小学校の先生数は増え、採用予定者数は増加しています。一方、小学校免許授与件数は横ばいや減少しています。大学卒業で免許状を授与されると考えれば、22歳人口が減少しているので、要因としてはその影響も考えられます。
1つ目の見直し内容は、小学校への「体育専科教員」の採用になります。これは志願倍率の高い「中学校・保健体育」の受験者において、小学校教諭の免許がなくても、小学校の「体育専科教員」の併願を認める仕組みです。合格予定者数は10名程度で、小学校の「体育専科教員」として採用になります。ただし、採用後、概ね3年以内に小学校の免許を取得していただきます。なお、小学校または中学校で3年の実務経験があれば、最低12単位の取得で小学校教諭の免許を取得可能です。小学校に「体育専科教員」を配置するメリットは、子どもたちにとっては技能教科の専門性や安全性の向上、他の学級担任にとっては授業の空き時間を確保することが期待できます。
2つ目の見直し内容は、受験資格の拡大「中学校または高等学校の教員免許状を持つ者」(小学校教諭への転換)ということで、小学校教諭の免許は持たないが、「中学校や高等学校の教員免許を持つ者」について小学校教員の受験を認める仕組みです。試験内容は一般選考と同じ内容で、SPIも可能とします。合格予定者数は40名程度で、合格後3年の猶予期間内に、小学校免許を取得し、小学校免許を取得できた段階で、教諭として採用します。猶予期間に小学校の免許が取得できない場合は、不採用となります。2026年度の試験合格後、猶予期間3年間で、小学校免許を取得すると2030年に採用というようなスケジュールです。 希望者につきましては、中学校や高等学校の免許をお持ちですので、講師としての勤務は可能です。なお、中学校の免許を持つ者の場合、小学校または中学校で3年の実務経験があれば最低12単位を取得することで、小学校の免許を取得可能となってございます。 小学校の制度の見直しについては以上2点です。
特別支援学校教諭の倍率は上がっていますが、志願倍率が2倍に達してないという状況です。今年度の試験から小学校・中学校・高等学校の免許での受験を認めて、一定数の志願者に受験していただいています。来年度からの見直しは、教員免許状がない社会人経験者の採用です。民間企業等で3年以上の勤務経験がある方で、 「教員免許を持たない方」の受験を認める仕組みでございます。試験内容は一般の受験者と同じで、SPI3による受験も可能とします。合格予定者数としては10名程度、合格者は猶予期間3年間の間に、小・中・高いずれかの教員免許を基礎免許として取得していただきます。特別支援学校の場合、小学部・中学部・高等部がありますので、基礎免許を取得していただいた段階で、教諭として採用になります。教諭として採用後、概ね3年間以内に、特別支援の免許状の方を取得していただくことになります。特別支援学校の免許状は基礎免許がないと、免許が取れませんので、この形での取得ということになります。来年度に採用試験に合格した場合は、猶予期間の3年間の中で基礎免許を取得後、採用となり、特別支援学校の免許を取得していただくという手順になります。なお、希望者には、猶予期間中、「期限付き実習助手」、「期限付き寄宿舎指導員」など、免許状がなくても従事可能な業務を紹介いたします。
勝田中等教育学校におけるイマージョン教育について
(資料「勝田中等教育学校におけるイマージョン教育について」に基づき説明)
イマージョン教育とは、英語以外の教科の授業を英語を使用して実施することで、言語、教科内容、双方の習得を進める教育手法です。導入背景としましては、急速に進展するグローバル社会で、複数言語の習得に対する社会的要請の高まりが挙げられます。現在、小学校でも英語が教科となり、中学校・高校で、英語を言語活動の1つのツールとして、海外へ留学する生徒や、県のNGGLという事業において、ワールド・スカラーズ・カップのような大会にも出場している生徒もいます。ねらいとしましては、英語以外の教科の授業を英語で学ぶことを通して、実践的かつ高度な英語力と学びの力を育成するとともに、グローバル化に対応した多文化共生の基盤づくりを推進していきます。2026年度入学生より、イマージョン教育を実施し、1(中学1年生)~2年次(中学2年生)は学年全体(105人予定)で、体育、音楽、美術、技術、家庭の実技科目でイマージョン授業の導入を進め、実技科目にある程度の専門性を有する実技科目担当のALTと、教科の専門家である日本人教員が2人ペアで授業を行っていきます。調整担当教員の配置なども含めて検討をしていきます。3(中学3年生)~6年次(高校3年生)は希望者による最大35人のイマージョンコースの編成をしてまいる方向です。取組としては県内の県立高校で初となります。3年次~6年次は実技科目以外への教科にも拡充していきますので、例えば、数学の場合、数学の専門家で、英語で授業を行える教員を配置するということも検討し、活用を予定しております。今後のスケジュールは、 10月11日(土)に勝田中等教育学校における学校説明会がありますので、当日来てくださった受験を希望している小学校6年生の皆さんと保護者の皆さんに、説明を予定しています。来年度の入学者選抜は、 従前の通りの実施になります。
今回、取組を進める勝田中等教育学校は、令和3年度に開校して、今年度5年次生(高校2年生)まで在籍しており、来年度にちょうど1期生が6年次生になるところです。これまでもグローバル教育や英語教育の取組に取り組んでおり、文部科学省のワールド・ワイド・ラーニングコンソーシアム構築支援事業(WWL)において、令和6年度から、県内初の拠点校に採択されて、世界標準の英語でリーダーシップなどの育成を図る取組を進めています。グローバル・コンピタンス・プログラム(GCP)では、1~3年次生においては、週に1時間の総合的な学習の時間に「英語という教科で英語を学ぶ」のではなく、 「英語で学ぶ」環境に触れることで、自然に高い英語力を身につけるような取組を行っております。勝田中等教育学校においては、海外留学制度を整備し、毎年、希望者が海外に留学しています。卒業生の進路(現在は勝田高校)としましては、卒業後、海外大学に進学される方もいるという状況の中で、来年度からイマージョン教育をスタートしていくところでございます。
なお、詳細については、この後、県と学校で準備委員会を設置し、準備委員会で、授業の中身、様々な教育に関すること、このイマージョン教育に関することについて検討を重ね、4月からスタートするときに、生徒たちや保護者の皆さんがよく理解をした上でスタートしていただけるように取組を進めていまいります。
本日の発表項目に関する説明は以上になります。
茨城県教育庁 総務企画部 総務課 総務担当(広報・広聴)
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5148
FAX番号:029-301-5139
メールアドレス:kyoikusomu8@pref.ibaraki.lg.jp