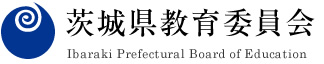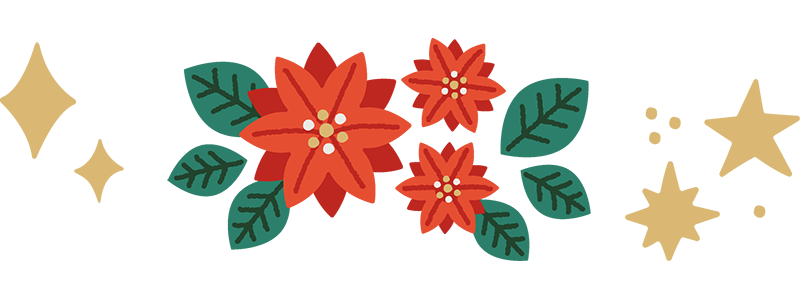お知らせ
【掲載内容の一部に訂正がありました】令和7年度茨城県いじめ問題対策連絡協議会
掲載内容の訂正について
令和7年9月2日に公開した「令和7年度茨城県いじめ問題対策連絡協議会」の情報において、10日後の9月12日に一部訂正がありました。
その間に情報をご覧になった方には大変申し訳ございませんが、以下の点について再度読み直してくださいますようお願い申し上げます。
訂正のあった項目
全体協議
- 学校におけるいじめ問題の現状と課題
- ネットリテラシー教育の現状と課題
| 日時 | 令和7年7月4日(金)13:30~15:30 |
|---|---|
| 場所 | 茨城県庁 |
| 出席者 | 学校関係、警察、法務、福祉等の33の関係機関及び団体等より32名 |
本協議会の概要
本協議会は「茨城県いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体が情報共有及び連携を図ることを目的として設置されました。平成26年7月に第1回が開催されて以来、今回で12回目の開催となりました。
会議冒頭において、本協議会の会長である県教育庁学校教育部の庄司一裕部長から挨拶がありました。概要は次のとおりです。
会長挨拶
いじめ防止対策推進法が平成25年に施行され10年以上が経過した。文部科学省によると、令和5年度のいじめ認知件数は過去最多である。これは各学校におけるいじめの積極的な認知が進んでいる証と捉えている。一方で、いじめによる生命・心身・財産への重大被害や長期欠席を伴う重大事態も過去最多となっており、初期対応の徹底と未然防止教育の強化が必要である。昨年8月に改定された重大事態調査ガイドラインにより、学校・県の対応が明確化されたが、SNS上や性的ないじめなど学校だけで対応困難なケースも増加している。これを受け、県教育庁に「生徒支援・いじめ対策推進室」を新設し、校種横断的にいじめ対策を推進している。
当協議会は、いじめ防止対策推進法第14条に基づき、関係各機関の連携のため平成26 年から毎年開催している。令和2年に茨城県いじめの根絶を目指す条例が施行され、社会総がかりでいじめに向き合うことの重要性が改めて確認されている。
今年度は「いじめの重大事態を防ぐ社会総がかりの取組」をテーマに、茨城県弁護士会及び教育庁の取組発表を行い、協議、共有する。引き続き全ての子どもたちが安全安心な学校生活を送れるよう、皆様のお力添えを賜ることを強く願う。
続いて、生徒支援・いじめ対策推進室と茨城県弁護士会の「取組発表」を実施しました。それぞれの取組発表について、各団体から質疑が行われ、いじめ問題への対策を様々な視点で話し合いました。
取組発表:生徒支援・いじめ対策推進室
文部科学省が行った問題行動等調査によると、令和5年度のいじめ認知件数は全国6位と高いが、認知件数が多いことは教職員の目が行き届いている証であり、逆に少ない場合は見逃しの懸念がある。重大事態の増加は問題だが、認知件数の増加は必ずしも悪いことではなく、教職員の目が行き届いている証として肯定的に捉えている。
いじめの多くは冷やかしや悪口から始まり、近年はパソコンや携帯電話による誹謗中傷や画像・動画の拡散が深刻化している。これらは表面化しにくいため、学校は警察等と連携して適切に対応することが求められる。
本県の生徒支援重点事項としては、児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、授業や行事を通じて自己肯定感・自己有用感を育む居場所づくりを重視する。また、自己理解を深め、主体的に問題を発見し解決する自己指導能力の育成を目指し、学習指導と生徒指導を一体化した授業づくりを推進している。併せて教育相談体制を整備し、校内オンライン相談窓口の設置や一人一台端末を活用した心の健康観察の活用、スクールカウンセラー等の派遣や相談窓口の周知を強化し、早期発見・支援に努めている。スクールロイヤーによるいじめ予防教室や職員研修も行っている。
いじめの重大事態の調査に関するガイドラインが改訂され、いじめの重大事態を未然に防ぐために、平時からの備えなどが明記された。当室としては、すべての学校でいじめについて適切な対応ができるよう、各種研修会を実施し教職員の理解を深めている。
取組発表:茨城県弁護士会
いじめの定義は、平成25年のいじめ防止対策推進法により「被害児童が嫌だと思えばほぼ全ての行為がいじめ」と広く規定されている。これは滋賀県大津市でのいじめ自殺事件を契機に、学校の対応の不備が社会問題化したためだ。多くの教職員や保護者には、この広い定義への抵抗感や「加害児童に悪意がない場合もあるのでは」という疑問が根強い。しかし、早期発見と対応による深刻化防止が趣旨のため、軽微な段階でも丁寧に拾い上げることが重要である。
いじめ防止には、子供の言葉にじっくり耳を傾け、時間をかけて教育的指導を行う必要がある。加害児童も悪意が必ずしもない場合があり、断罪を避けつつ理解しやすい指導を行うことが望ましい。また、弁護士によるいじめ予防授業では、いじめが人権侵害であることを伝え、SNSなど見えない相手への想像力を促す内容が行われている。特に「いじめの4層構造」である、いじめる人、いじめられる人、はやし立てる人、見ている人のうち、見ている人である傍観者が行動を起こすことを促し、被害の拡大防止を図っている。
重大事態調査では、いじめの認知不足が最大の問題である。担任や学年、養護教諭など特定の教職員で情報が止まり、管理職やいじめ対策組織に共有されないケースが多い。また、スクールカウンセラーを十分に活用していない学校も多い。学校いじめ基本方針を再確認し、いじめ発生時の対応ルートを遵守することが求められている。いじめの認知件数は「増加」しても決して悪いことではなく、子どもたちが先生に相談できる信頼関係の証拠である。重要なのは、認知した問題が深刻化しないよう初期段階で丁寧に対応することだ。
いじめによる命の喪失を防ぐためにも、軽微な訴えでも見逃さず根気強く指導し、被害児童を守ることが求められている。弁護士会はこうした教育活動に尽力しており、関係者にも職務範囲での積極的な取り組みが重要である。
全体協議
全体協議においては、各委員からそれぞれの立場でいくつかの意見がありました。主な内容は次のとおりです。
学校におけるいじめ問題の現状と課題
- 学校現場においては、特にSNSを通じた見えにくいいじめが増加している。加害者、被害者の固定化を避け、成長支援の視点から対応する必要がある。また、教員は強い責任感を持ちながらも心理的負担や対応力不足を抱えており、孤立しないよう組織体制の構築が求められている。さらに、小中学校時代の被害経験を踏まえ、多角的な支援体制を整備し、生徒・保護者・教員が連携して取り組むことが重要である。
- 小中学校では、例えば月1回のアンケートを実施し、書かれた内容は個別や全員への教育相談に活用している。職員間では月例の生徒指導部会の実施とその共有や研修を通じ、全ての教職員のいじめ発生時の対応力を高めている。日々の情報共有と即日対応の徹底が重要であり、特に週末に問題が大きくなることから注意を促している。課題としては、小学生のスマートフォン所有が増加し、家庭での使用ルール作りが不可欠である。また、一人一台端末の普及に伴い、ネットの誹謗中傷や情報モラル教育が急務となっている。国の方針としても、情報活用能力や人権意識向上を重視しつつ、子供たちを守る対策が求められている。
- 特別支援学校では基本的に小中高等学校と同様の対応を行っているが、多くが知的障害のある児童生徒のため、いじめか障害特性かの区別が難しい。社会的に許容されない行為は「いじめ」として認知し、保護者と連携して指導している。日常的に「してはいけないこと」や「相手を尊重すること」を教え、学級づくりを推進しており、管理職への情報共有を速やかに行い組織として早期対応を図っている。特別支援学校長会と高等学校長協会が連携し、人権課題にも取り組んでいる。
ネットリテラシー教育の現状と課題
- スマートフォンの所持率は高校でほぼ100%、中学生で約90%、小学生6年生でも約70%に達している。小学生では家族でのルールづくりが80%超と多いが、中学生では減少し、約2割の家庭がルールを設けていない。子どもたちは主に動画視聴やゲームに利用し、オンラインでのトラブルや実際の接触事例も見られる。今こそ、家庭でのルールづくりを重視し、周知徹底の取り組みを強化すべきである。
- 小中学校では、総合的な学習の時間や道徳科等で情報モラルについて学習する機会がある。また、メディア教育指導員や通信会社を外部講師として招き、情報モラル教室を実施している。
- 高等学校では、入学生に対しスマートフォンの使い方を入学前に家庭で話し合わせ、入学日に家庭内で決めたルールを提出させることから始める。入学後は警察や携帯会社、外部専門家による講義を実施している。情報の授業でリテラシー教育を重視し、探究学習やPTA研修でも取り組む。学年や通年で多様な形態により、スマートフォン利用のルールやリテラシー向上を図っている。
教科指導と生徒指導の一体化
- 義務教育課では、小中学校の教育において「取組」として四つの視点を示している。第一に、一人ひとりの予習状況や興味・関心に応じた、分かりやすく楽しい授業づくりを推進している。第二に、互いを認め励まし合う共感的な人間関係を重視している。第三に、議論や協働的な学習を通じて自ら考え話合い、決定して実践する機会をつくっている。第四に、個性を尊重し安心安全な環境をつくり、児童生徒が認められていると感じる居場所づくりを目指している。
- 高校教育課では、平成19年度から全国に先駆けて道徳教育を実施している。道徳教育は学習指導要領に基づき学校の教育活動全体で行われており、生徒が自分の生き方を考える機会を提供している。具体例として、家庭科の「赤ちゃんふれあい体験」では命の大切さを実感させ、また特別活動の話し合いでは多様な意見を尊重し協働する態度を育てている。県では教職員だけでなく企業やPTA等多様なメンバーで構成する「道徳教育推進委員会」を設置し、学校だけでなく社会全体で道徳教育を推進する必要性を掲げている。
協議会の最後に庄司会長よりまとめの挨拶がありました。概要は次のとおりです。
庄司会長まとめ
本日は二つの取り組み発表があった。生徒支援いじめ対策推進室より、いじめ防止の重点事項として教科指導と生徒指導の一体化、自己肯定感の育成、教育相談体制の整備、SNS活用、即時対応の重要性が説明された。茨城県弁護士会からは早期発見・対応と、傍観者への働きかけによる予防授業の実施状況が報告されたが、情報共有の停滞が問題点とされた。協議を通じ、いじめは社会全体で取り組む課題であり、「絶対にしない、させない、許さない」意識の醸成が不可欠と改めて確認したところである。人間関係のトラブルは避けられないが、子供たちに適切な振る舞いを伝える必要がある。迅速かつ慎重な初動対応、被害者の心のケア、加害者指導、再発防止を含む環境整備が重要である。日常の小さな気付きと優しさがいじめ防止の力となる。今後も子供たちの健やかな成長に協力をお願いしたい。
お問い合わせ先
茨城県教育庁 学校教育部 生徒支援・いじめ対策推進室
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5229(生徒支援担当)
電話:029-301-5262(いじめ対策担当)
FAX:029-301-5269
メールアドレス:bunka@pref.ibaraki.lg.jp