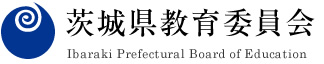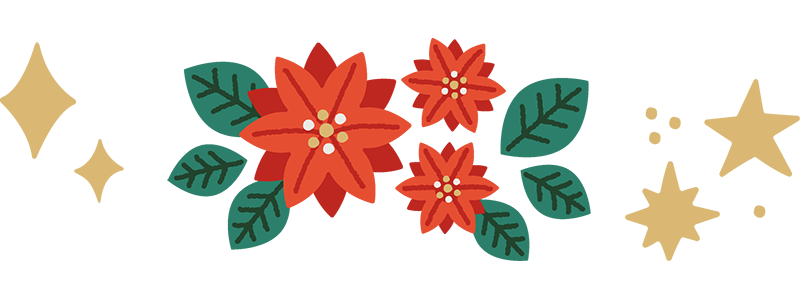優秀賞 神栖市立神栖第一中学校
地域と学校が連携した防災教育の在り方



これまでの課題と活動のねらい
課題の把握と設定状況
学校では学校保健安全計画に基づいて各種保健安全教育が行われている。しかし、校外における自然災害時の危険回避に関して学ぶ機会がほとんどない。そんな中、本校は今年度より学校運営協議会(コミュニティースクール)の運用を開始した。この機会に地域の方と一緒に防災教育に取り組み、生徒達に自然災害時の危険回避能力を育成したいと思い、本テーマを設定した。
活動のねらい
- 自然災害の発生を自分事として捉える。
- 生徒達の危険回避能力を育成する。
計画と実践の状況
計画
- 避難訓練(4月、9月、1月)
- 引き渡し訓練(5月)
- 生徒会と学校運営協議委員との防災ミーティング(6月、11月)
- 全校での防災集会(9月)
- 防災シンポジウム(12月) 講師:筑波大学 梅本准教授
実践の状況
下記PDFをご確認ください。
成果と今後の課題
成果
- 日頃防災を意識している生徒の割合は37.2%だった。しかし、「防災集会を通して、地震津波に対しての意識は高まりましたか。」という問いに対して81.3%の生徒が「高まった」と回答し、生徒達の防災意識を高めることができた。
- 東日本大震災の神栖市の被災状況を具体的に知らない生徒の割合は21.9%だった。しかし、防災集会の後「地域の方の体験談を通し、東日本大震災を振り返る良い機会となりましたか。」という問いに対し、97.9%の生徒が「なった」「ややなった」と回答しており、自分たちの住んでいる地域でも自然災害が起こる可能性がある事を学習できた。
- 「防災について、学校だけではなく家庭でも話すことは、今まで以上に大事だと思いますか。」という問いに対し、「思う」「やや思う」と回答した生徒の割合は97.9%だった。生徒が学習内容を家庭に伝え、家庭の防災意識も向上することが期待できる。
今後の課題
- 一過性の取組とならないよう、次年度以降も計画的に地域と連携した防災教育を取り組む必要がある。
- 今まで以上に保護者・家庭とも連携して、防災教育に取り組む。