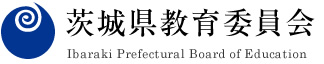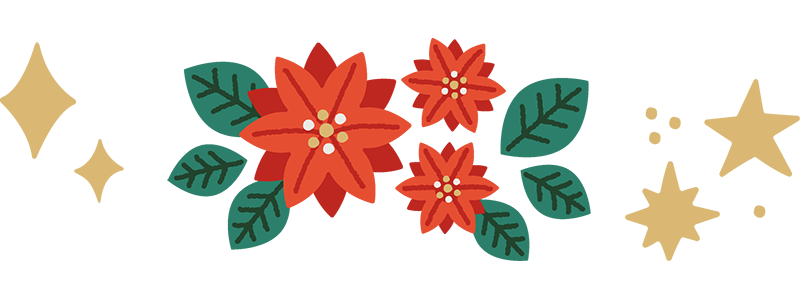優秀賞 守谷市立愛宕中学校
生徒主体の学校保健委員会の在り方



これまでの課題と活動のねらい
課題の把握と設定状況
学校保健委員会を立案する前の段階で戸惑うことは、日時や参加メンバー、議題のテーマである。マンネリ化しないよう、議題や形態の在り方を探っていくことが重要である。現在、愛宕中学校区(愛宕中、守谷小、郷州小)では、小中連携の一環として、養護教諭が互いの学校保健委員会に出席している。他校の協議内容から、客観的な視点で学ぶことが多く、とても参考になっている。
本校は10年以上前から、生徒主体の健康教育を推進することをねらいとして、生徒参加型の学校保健委員会を開催している。
令和6年度は「学校・地域における安全」をテーマに、3年生を中心に話合いを重ね、生徒の視点から安全点検や改善点をまとめ、アンケート調査を実施し生徒の実態を分析して発表した。学校医等、警察署、保護者、教員、生徒が協議し有意義であった。
今後も、生徒自身の自己管理能力を育成するため、本テーマを設定した。
活動のねらい
- 学校保健委員会を学校保健・安全計画に位置付ける。
- 地域や関係機関と連携し、学校保健委員会を開催する。
- 生徒保健委員会が中心となり活動することで、生徒が自ら健康安全を意識し、自己管理能力を育む力を高める。
計画と実践の状況
計画
- 学区の小中学校で学校保健委員会のテーマや開催時期等との意見交換(4月)
- 生徒保健委員会組織作り(4月)
- 生徒保健委員会が学校保健委員会に向けての活動(5月~11月)
- 学校関係者、PTA役員に協力依頼(10月~11月)
- 愛宕中学校保健委員会開催(11月)
- 学校保健委員会の報告と全校での共有(12月)
実践の状況
下記PDFをご確認ください。
成果と今後の課題
成果
- 保健委員の生徒は、学校保健委員会を開催するにあたって、テーマについて真剣に考え、話合い、発表までの準備を丁寧に行うことができた。
- 令和6年度は「安全」をテーマに、警察署員の話を自分事として捉えて聞いていた。また、全校生徒への報告も他の生徒が理解しやすいように、効果的にまとめることができた。
今後の課題
- 地域における学校保健委員会の在り方
- 情報共有と効果的な発信の仕方