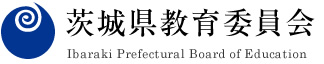北茨城市立華川小学校
実践研究テーマ
学校・家庭・地域でつくる華川っ子〜コミュニティ・スクール設置委員会と地域産業「自然薯栽培」を通して〜
学校全体としての取組
地域資源「自然薯」(北茨城自然薯研究会の支援)の栽培
目的
華川地区の特産物である自然薯の栽培を通して、種芋から大きくなるまでの過程に見られる感動を味わったり、天候や生育環境に配慮するなどの苦労を感じたりすることで、主体的に学習しようとする態度や自分たちの地域への愛着や理解を深めようとする態度を育てる。
内容
- 自然薯について地域の農家の方に話を聞いたり、自分で調べたりして地域の特産物についての理解を深める。
- 床づくり、苗植え、水やり、雑草取りなどの世話をする。
- 成長したものを収穫し、各家庭で味わう。
6月 割りばしの印にそって植え付け

12月 収穫 「とい」の中に入って育つと、まっすぐに成長

その他(華川っ子いきいき体験学習)
1・2年「町たんけん」
生活科の学習で、華川町にある商店や郵便局などに見学に行き、学区内の探検をしました。お店の人にインタビューして、売り場や働く人たちの仕事のようすを知ることができました。

3・4年 学校間連携チャレンジプラン「県庁見学」
石岡小学校と合同で、水戸市にある茨城県庁に見学に行きました。県庁の役割を聞いたり、施設の中を実際に見たりしたことで、はたらく人たちについて学ぶことができました。

5・6年「いのちの教育」
助産師や保健師の方から「いのちの大切さ」について教えていただきました。妊婦体験や赤ちゃん人形の抱っこ体験などをすることができました。

縦割り班活動(縦割り班清掃)
1年生から6年生までを縦割り班に分け、異学年で協力しながら、年間活動をしています。
学校評議員会(コミュ二ティ・スクール設置委員会)の充実
コロナ禍のため、給食試食は未実施
第1回 6月24日(金)
コンプライアンス推進委員会本年度の学校経営について
- 授業参観
- ICT活用
第2回 11月25日(金)
本校教育活動の取組状況、学校運営協議会について
- 授業参観(保護者参加)
- ICT活用
第3回 2月24日(金)
学校関係者評価委員会学校運営協議会準備会
- 授業参観(6年生を送る会)
家庭・地域等との連携の工夫点
郷土愛を育む素晴らしい環境
自然薯栽培にあたっては、北茨城自然薯研究会の支援を受け、雨どいや栽培に適した山砂を使用した北茨城方式で行っている。地場産業の理解・地産地消の点からも、良い環境に恵まれている。さらに、青少年健全育成華川支部・青少年相談員・学校評議員・安全ボランティアの方々は、本校の卒業生や元PTA役員等であり、三世代にわたって、地域との懸け橋になっている。
事業の成果と課題
成果
- 地域の特産物である自然薯を小売店で買ったり、収穫物をもらったりするのではなく、自らの手で植え付けしたものが成長して成果物となるのだ、ということを実感することができた。
- 植え付け位置からずれた種芋は地中深くに成長し、穴を掘り進めないと収穫することができず、生産者の苦労を感じることができた。
- 11月に行った「華小祭り」にて、ゲストティーチャーへのお礼の場を設け、感謝の気持ちを伝えることができた。
課題
- 感染症対策のため昨年に引き続き、収穫物は家庭への持ち帰りとなった。タブレットパソコンの持ち帰りも考慮すると、自宅での調理例を写真に撮るなどができるので、食すまでの過程を記録に残し、総合的な学習の時間や生活科との関連性を高めていきたい。
令和4年度 モデル校での取組
お問い合わせ先
茨城県教育庁 総務企画部 生涯学習課 学習支援担当
〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6
電話:029-301-5322
FAX:029-301-5339
メールアドレス:shogaku2@pref.ibaraki.lg.jp