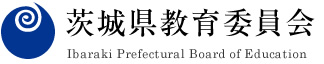いばらきの文化財
文化財種別
国指定 有形文化財 考古資料
重要文化財
茨城県風返稲荷山古墳出土品
いばらきけんかざかえしいなりやまこふんしゅつどひん
かすみがうら市
霞ケ浦沿岸に築かれた古墳時代後期末(6世紀末から7世紀初頭頃)の前方後円墳からの出土品で、全53点で構成される一括のものとなります。
2基の埋葬施設やその傍から出土した豊富な副葬品(ふくそうひん)群で、銅鋺(どうわん)や金・銀で装飾された武器・馬具などが特徴で、特に銅鋺は小型で蓋(ふた)と承台(うけだい)を伴い、姿形も優美です。独特な形状で希少な棘葉形杏葉(きょくようけいぎょうよう)を含む2組の馬具は、遺存状態が極めて良好で、当時の輝きを現代に伝えています。また、金銀装の頭椎大刀(かぶつちたち)や金銅装の円頭大刀(えんとうたち)などの数量豊富な装飾付大刀(そうしょくつきたち)を有しています。
これらは、最末期の前方後円墳における副葬品の組み合わせを示す好例であり、この時代における金工品の種類や製作技術、変遷をみるうえでも重要なものです。
(写真提供 かすみがうら市教育委員会)

茨城県風返稲荷山古墳出土品
| 数 | 一括 |
|---|---|
| 指定年月日 | 令和5年6月27日 |
| 所在地 | かすみがうら市歴史博物館(かすみがうら市坂1029-1) |
| 管理者 | かすみがうら市 |
| 制作時期 | 古墳時代後期末 (6世紀末から7世紀初頭頃) |